
海外での学校生活って、実際どんな感じなの?
昨日、子どもが通う学校で、親と教師がカジュアルに話す「コーヒータイム」に参加する機会を得ました!子供は現在コスタリカのとある学校に通っています。
そこで目にしたのは、親の意見を教育現場に取り入れ、カリキュラム改善にもつなげようと、学校の方向性を説明するとともに、次々に質問を投げかける先生たちの姿勢。まさに「学び続ける教員」の姿。
ほとんど日本での学校経験しかない私(数十年前の実情しか知りませんが)にとっては、驚きと感動の連続でした。
この記事では、私の体験を通して見えた海外教育の魅力と、親として感じた学びのポイントをリポートしようかなと思います。
初めて体験した親と先生のカジュアルな対話

海外の学校では、教師と親が気軽に会話できる場が用意されることがあるようです。私は、教育をすべて日本国内で受けていて、こんな場が「先生陣と親」との間に用意されることにとても驚きました。
私が参加したコーヒータイムは、学校側によるアレンジ。「学校での教育についてカジュアルに意見交換しましょう」という連絡通知がメールで来ました。
授業内容や学習環境について率直に意見を交わし、学校側も真剣に耳を傾けてくれます。このカジュアルな交流は、親が積極的に子どもの教育現場を知ることができ、また学校側と関わることができる機会としてとても有用だと感じました。
先生たちの「学び続ける姿勢」に触れて

先生たちは単に教えるだけでなく、常に学び続けています。親からのフィードバックを受け取り、どう教育現場に活かせるかを考え、カリキュラムに反映する。
その姿勢を間近で見て、「こんな風に教師が自分自身も成長し続けようという姿勢があるなら、子どもたちの学びも豊かになる」と実感しました。
例えば、ある親は、
「うちの子、語学の授業があるのに全然話せるようにならないのよね。どうにかもっと生徒に練習させる機会を設けるようなことはできないかしら?」
と、とてもカジュアルに質問。
それに対して、先生側は「それなら、彼の語学の先生にも聞いて、何が彼の学習状況を改善できるか話し合いの場を設けましょう。もし可能なら、ボランティアになるけど、その言語を話したい人たちを放課後に集めて話す会を設けることを検討してもいい。」というような感じ。
大変ざっくばらんで、和気藹々と「何ができるかな、これやってみたら改善するかな。」とブレインストーミングをし、それをどう実際の教育に反映させられるかを建設的に考えるような感じです。
先生自身も自分の毎日の「気づき」を親に共有します。「今日生徒にこう言われて気づいたから、今後に反映するゎ。」とか。
なんというか、とてもプロアクティブ。自ら環境を改善し、生徒をよりよく育てようとするのが、話し方のすべてから感じられます。
海外教育から学んだ、親としての気づき

この体験は、私にとって固定概念を覆すような内容でした。
私の中では、「親が教育現場に気軽に意見を言うこと」、「先生が教育の改善を目指し、学習し続ける環境を設けること」、「親も学校の一部として関われること」、こういったことは、私が学生として過ごしてきた教育現場では聞いたことが無い内容だったためです。
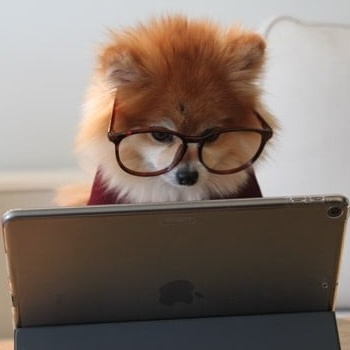
私が行った学校が、そういう開けた教育現場な学校じゃなかったってだけかな?
なぜか、私は「親は教育に口出しすべきでない(プロに任せる)」、「先生はカリキュラムに従っているので、そのシステムを乱すような意見申し入れはしてはいけない」、というような「教育現場に親は口出しすべきではない」イメージを勝手に作り上げていたようです。
当地の風土としては、「『子供のためのより良い環境』を、随時意見交換をして、意見を反映し作り上げる」というもの。なんというか、目から鱗でした。
子どもの学びが親の関わりによって改善され、そして親自身も教育について学び考える機会を得ます。当地では、教育が教師と親、子どもを含むコミュニティ全体で作られていることを実感しました。
海外生活・移住を考える方に

この学校体験から感じたのは、海外教育は親子双方にとって学びのチャンスがある可能性が高いということ。
先生自身が自主性を育み、リーダー的思考を以て物事を進めていこうという姿勢は、生徒にも引き継がれます。実際にこの学校では、生徒が自主性を持ち、主体的に物事を進めることを教育の基礎の一つとして啓蒙しています。
親にも意見が求められるので、自分の子供に何が起こっているのか普段観察し、家での状況を踏まえ先生に意見を伝えることになります。
ちょっと大変な気もしますが、親の声をシャットダウンするのではなく、逆にカジュアルに受け入れる土台が作られていて、親も子供の学校生活をよりよくする一つのコマとして機能できるように環境が整えられていることは大変ありがたいことだと感じました。
このように親も主体的に学校の環境に参加できる風土があると、親自身も教育に考えを向ける必要も出てきます。当地での学校生活を実際に体験することで、親としても教育者としても成長できる可能性があると感じられました。
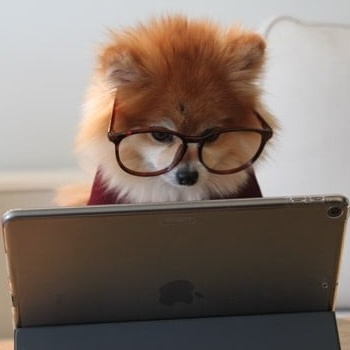
今回の話し合いで、「この学校が取り組んでいる教育方針の参考書が図書館に入れられ、親が借りられる仕組みを作ることも決定」しました。すごい。
「私も学ばなきゃ!」と思わされました。
まとめ|学び続ける先生と親子で育つ学び
親も子も巻き込む教育の文化、そして教師の学び続ける姿勢。
そんな教師の背中が見られる環境の中で子どもは学ぶ。そして親も子を通じて学び、家庭と学校がともに成長する環境が当地の学校では作られていました。
海外の欧米系の学校って、日本よりも帰宅時間が早いんですよね。うちの子は毎日3時くらいに帰ります。
そういえば、私が米国で大学行ってた時も、午後1時には授業は終わってました。後は自主学習。(宿題の量が半端なく、夜中まで宿題に追われます。)
家に1人で鍵っこを残すことはできないので、自ずと、親は子供といる時間が長くなります。親が子供と過ごす時間は、日本の倍くらいはあるんじゃないかなという気がします。
社会の仕組みが、本当に「子育て」中心なんですよね。
不思議なのは、多くの父親、母親が積極的にこうした学校のイベントに参加していること。ボランティアをしていることもよくあります。「会社は…?仕事は…?」って思わず質問したくなります…。
この記事が、海外生活や移住を考える方にとってのご参考になれば幸いです。







