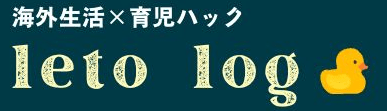親がどうしても意見を聞き入れてくれない…。聞く耳持たない。
頑として意見をゆずらない。どうしたら、私の意見に近づけられるだろう?このまま親に従ったら、未来が私が思い描く通りにすすまない。
この記事を読んでいるあなたは、頑固な誰かの意見を変えられず困っている方ですね。
相手が自分と合わない意見を持ちだしてきたときは、相手の話に対し、対立的に話してしまいませんか?負けじと意見を戦わせ、相手に自分の意見を押しつけようとしてしまう。
戦闘モードで話すんですよね。身近な人間であればあるほど、この傾向が出ます。
そんな対抗する議論の結果、どっちかが「勝った!」または「負けた!」ってなって、どちらかが相手の意見に譲るでしょうか。
大抵どっちも折れずに、自分の意見をキープしようとします。そして、余計それぞれの頑固な意見に固まります。
どちらかが「論破した!」って自己満足することがあるかもしれませんね。でもどっちも納得してないんですよね。論破された方は、納得がいかなくてモヤモヤが残ります。
その話し合いが未来の指針を定めうる議論だと、とても困ります。
なぜなら議論の方向性が現実に基づいてどちらが本当に正しいのか、ではなくて「自分の意見を相手にのませられるか否か」に軸が移り、正しい議論が見えなくなるからです。
結果、現実が反映されていない本当に困った結論に至ることもあります。
この記事では、相手の意見を変えるための心理学を紹介します。この記事は、こんな方に向いています。
この記事を読めば、頑固な相手の意見を変え、自分の思う方針に近づけられる可能性が上がります。ただし、長期戦です
「相手の意見を変えなければならない…」と必死な方にお読みいただければと思います。
それでは、ご紹介していきます!
説得する心理学の技術|敵ではなく、味方になる【大前提】

早速、結論からいいます。相手を自分の思う方向に向けたいのであれば、
「相手の敵ではなく、相手の味方になる」のが有効です。
「え?相手が逆の意見なのに?」と思いますよね。
相手を自分の思う方向に導く大前提として「自分は相手の理解者」なのであるという態度を示し、相手に敵でないことを認識させる必要があります。
具体的にやることは以下のとおりです。
議論を開始しはじめたときの相手の心理はどうかと言うと、「自分の言うことに理解を示してくれない悪い人間には、自分も理解を示さない」状態です。
そのため、まずは信頼関係を相手に認識させる必要があります。なので、相手に対して「自分はよい人物という印象」を与えます。
普段からも相手の言ったことが後で間違っていたとわかったとき、「だから私はそういったでしょ!」だとか、相手をはずかしめて、叩きのめすような態度も、相手に敵意を抱かせます。なのでNGです。
仲間であるはずの人でも敵意を抱くと、残念ながら敵意は増幅します。そして、あなたに対しさらに敵意のある言葉を返すようになります。
不毛な対立論を避けたいと思ったら頭に入れておくべきなのが以下の3つのことです。
1つずつ見ていきます。
相手が敵意を向けてきても、同じ土俵にのぼらない

話し相手と意見の対立をしそうになるときってわかりますよね。その気配を感じ、議論を避けたいなら、同じ土俵に乗らないようにします。
相手が対抗意見を投げてきたって、自分はそれを返す必要はありません。
敵意に対し敵意で立ち向かっても、状況はさらに対立する一方です。友好的にはならないですね。
重要なのは、相手の意見をよく聞くことです。そして、相手に「自分が相手をよく聞いていること」を理解させます。相槌をうったり、相手の言うことを繰り返してもいいですね。
「相手の言うことを信じられない」と思っても、とりあえず聞きます。
自分はあっている/相手は間違っていると決めつけない

「この人物は、人の気持ちを傷つける」と無意識に相手の態度を決めつけ話す人がいます。ですが、実際は話相手を傷つける意図を持って話す人なんてそう多くはありません。
価値観の違いなどにより勘違いが起きて、人を傷つける人と決めつけられてしまう人もいますが、それはイメージの問題で、実は悪人じゃないこともあります。
誰かに「あなたは悪い人だ」だとか「バカだ」と決めつけられて気持ちがいい人はいないですよね。もしあなたが「バカだ」と決めつけられた態度で相手から話しかけられたら、どうしますか?
たぶん「絶対に自分の意見を強く伝えて対抗し、絶対に意見を変えない」と対抗心を燃やすはずです。
だから最初から「相手の意見が絶対間違っている」とは考えないで、相手の立場や意見と自分の意見がどこなのかを見極めます。
相手も自分もどっちも間違っている可能性だってありますからね。
議論はやめてもいいと理解する

議論がはじまったとしたって、途中で議論をスパッとやめるのもありです。
議論が建設的じゃないときもありますよね?議論が白熱しすぎて、信頼関係を失って関係にヒビがはいり、友人や恋人じゃなくなることもあります。
何か関係性を悪くする前に、そんな議論はやめればいいんです。SNSでも議論が白熱しすぎて、お互い引きどころが見えなくなることもありますよね。不毛な場合もあります。
相手の意見を変えるのには、時間がかかります。誰かの意見を聞いたからって「はい、意見変えます。」って言う方はおそらく少ないですよね。
意見は、誰かにいわれて変わるものではなく、自分の中で何かに気づき徐々に変わっていくものです。
説得する心理学の技術|信頼関係(ラポール)のルール

会話をするとき、相手と信頼関係を構築するためのルールがあります。これを心理学ではラポールといいます。
ラポールのルールでは、具体的に会話を以下のように行います。
会話をするときに、まずはじめに聞く姿勢から見せると、相手のあなたに対する敵意を減らすことができます。
説得する心理学の技術|事実は突き付けられるものではなく、自分で気づくもの

相手を説得するのに「相手に事実を突きつけて理解させようとする」ことってありますよね。でもこれは効果が薄いようです。
1940年のカート・リーウィン(Kurt Kewin)による研究によると、「なぜ振る舞いを正さなくてはならないのか」の講義をしたところ、3%の人しか効果が見られなかったそうです。
一方で、同じ振る舞いについて自分たちで理由を考えさせ行動を考えることを促したところ、37%の人が振る舞いを変えるに至ったとのこと。
ここから見えるのは、人にただ言われたアイディアに対しては行動しない傾向にあるのに対し、自分たちで理由を考えたことには行動を起こすということです。
行動を起こさせるには、「自分で気づかせる」必要があるんですね。
説得する心理学の技術|無知を自覚させる

意見が対立する会話をするとき、皆何かをさも知っているかのように話しますが、本当はよく知らないのに話しています。皆、知ったかぶりして話しています。
例えば、携帯電話を例にとってみましょう。どうして携帯電話で他の人と話せるか説明できますか?その道の専門の方でもなければ、その仕組みについて正しい説明はできないはずです。
でも、「携帯」が話題になると、さも携帯電話のことを知っているかのように話します。要するに、誰でも、実は話していることに対しそんなに知識が無いこともあるということ。
なので、知ったかぶりの意見を持って議論を振りかざす人には、カウンターパンチの意見を振りかざすんじゃなくて、丁寧に質問していきます。
例えば、こんな感じです。
「もっと細かいところまで話してくれる?わからないから、もっと教えてほしいんだけど?」
「自分は無知なので教えてほしい」と伝えると、相手はさも自分には知識があるという態度で説明を続けようとします。そして、説明につまづきます。
答えられないから無知さが露出するんですね。そうすると、話している本人が自分の無知さを自覚し、自分の意見に対して疑問を持つようになるわけです。
少なくとも、極論をいっているときは、それを極論でないようにするくらいの効果があります。自分の振りかざす意見が何をベースに成り立っているのか説明できなくて、自分自身が揺らいでしまうわけです。
もし、あなたが相手に対し、カウンターパンチの意見をいっていたら、相手からは敵意むき出しの意見が返ってきたかもしれませんよね。けど、この方法であれば相手は受ける質問で自滅します。
説得する心理学の技術|自分の言っていることを数値で示させる
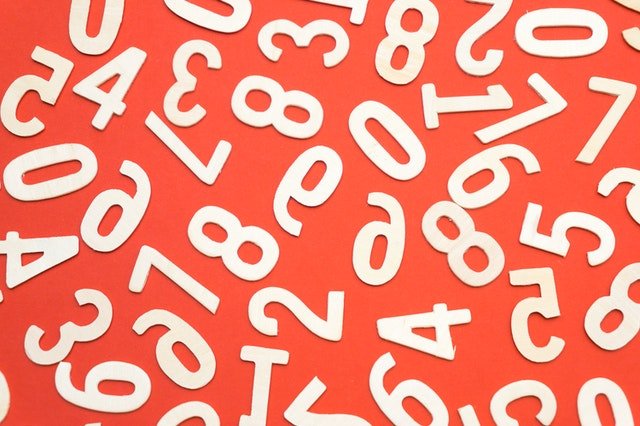
相手が極論を振りかざしている場合には、相手に数値で物事を判断させると少し落ち着いて考えてもらえます。
例えば、こんな会話があるとします。
相手 「この国の政治は、茶番だ、まるで話にならないっ!」
あなた「北朝鮮の政治の茶番さが10点中9点だとしたら、この国の政治はどれくらいだと思う?」
こう聞かれたら、ちょっと冷静に自分に発言を分析してしまいますよね。
ほかの1例です。
あなた「あなたの意見は、10点満点だとしたら、何点くらい自信がある?」
相手「8点」
あなた「なんで9点じゃないの?」
ここで、相手は、なんで自分が自信を持って10点満点をつけられないのか考えます。
説得する心理学の技術|確認していない事実を理解させる

自分の意見をまったく変える気が無い相手に、率直に、相手に自分の信念に疑問がないか質問します。
例えば、
「どんなときに、(あなたが)信じてることが、間違ってる可能性がありえると思う?」
などです。
ほかの例としては、
「もし(あなたの)言うことにまったく再現性がなかったら、自分の意見を変える?」
などです。
「いや、僕の言うことは100%正しいから、覆らない」
と言う人もいますよね。
でもそれって、誰も確認したことがない事実に対して根拠もなく自分で勝手に太鼓判押してるわけで、全然信ぴょう性がありません。
それを自分でわかって言ってるわけです。それって自分自身の信ぴょう性もおとしめていることになります。後で言ったことを後悔する気がしませんか?
ほかにも、
「もし幽霊が実体化して、『これは間違ってる』って言ってきたら、僕がいってることは信じられないかもって認めるかもね。」
とか、現実で起こりえないことを言う人もいるかもしれないですね。これはイライラします笑。
まぁこれも、結局自分が話していることに信ぴょう性がないことを裏付ける内容になります。要するに、議論に対して、真摯に向き合ってないと言うことです。
自分から自分は真摯じゃないことをはっきりと言ってしまっているわけです。
説得する心理学の技術|強い信念は価値観とアイデンティティに直結する

信じていることがもう真実とはかけ離れていても、信じるといい切る人たちもいます。もう、それをいい続けるのがアイデンティティになっている人たちです。
例えば、UFOを信じる人たちや、ネッシー、ビッグフット、ツチノコを信じる人、宗教もそうですね。
そんな人たちには、「UFOは存在するかしないか」は問わず、「どうしてUFOは存在するという信念に知ったのか」を聞く、無知を自覚させる方法をとります。
質問としては、
「UFOは(あなたにとって)とても大事な信念みたいですね。何がその信念のもとなんですか?」
などですね。
あなたが「他の普通の人も信じると思います?」と聞いてみて、「そうですね。」といわれたら、
「私も自分は結構普通だと思うですけど、信じるに至らないんですが、どうしたら信じられますかね?」
と聞いてみます。
信念とアイデンティティが直結している程である場合、上記のように相手に無知さを自覚させるための種をまいたところで、信念はそう簡単に覆らないのが実際のところです。
あとは、種まきした芽が出て、信念が覆るか否かは本人たち次第です。
いずれにしろ、真向から反論してお互いに意味のない罵りあいをするよりは、ずっと平和裏に会話が進み、自分の持っていきたい方向に相手を導くことができます。
時間が経てば、相手の信念に少し変化が現れるのが見られるかもしれません。
説得する心理学の技術|激しく同意する
ほかにもこんな方法もあります。それが、
激しく相手に同意する
ことです。
例えば、相手が「こうだと思う」と意見を言ってきたら、「そうだね、その通り。絶対その通り、そうに決まってる、100%そうだ。」と賛成しまくると、「え、そこまでとは思わないけど…」と逆に自分から自分の意見を否定の方向に持っていくというものです。
相手の心の動きを追うとこんな感じです。自分の最初の意見のレベルを保とうとするため、自分の意見が行きすぎると引き戻そうとする心理が働きます。
相手 「これは〇〇だと思うんだよね。」
心の中:…少し思いつきで思った意見
あなた「そうだね、そうに決まってる、絶対そうだ」
相手 「え、そこまでじゃなくて、まぁ〇〇だと思ったくらいで」
心の中:…「絶対」じゃなく、「少しの思いつき」のレベルに戻さなくちゃ
この研究は、イスラエルのテルアビブ大学が行った研究によります。
150名のイスラエル人の男女について、パレスチナ問題を題材として実験をしたものです。この方々を2つのグループに分け、片方には普通のコマーシャル、もう片方にはイスラエルのプロパガンダ(イスラエルが正しいという賞賛動画)を見せたそうです。
すると、なんと極論のプロパガンダを見せられた30%もの人がパレスチナ問題について意見を変えたそうです。
これはすごいですね。
なぜすごいかというと、パレスチナ問題は宗教問題でもあり、イスラエル人のアイデンティティに関わる内容です。なので、意見を変えることは難しい。けれど、極論を突きつけられると、逆に信念すら揺らいでしまうということです。
これを私たちの身近な例に例えてみます。例えば、あなたが「ベーガンは体にいい」という考えを持っていたとします。
それで、あなたに対し誰かが「ベーガンは100%よいに決まっている。全員ベーガンになるべきだ。肉は法律で規制すべきだ、肉を売るのは犯罪だ、野菜以外を食べる人は人でなし。」みたいな意見を言うわけですね。そうすると相手は「そこまで言ってない…」と議論を引き戻すということです。
ポイントは、
相手の意見を極論にして賛同する
ということですね。
これを応用すれば、いろいろな場面で使えますね。
留学を反対する親に対して:
「そうだね、その意見は絶対あってるね。お父さんとお母さんは留学なしで超完璧な人生を送ってきたし、日本では人生で必要なことは全部学べるし、日本語だけ話せれば生きていくのに十分な能力だし、日本だけ見てれば将来的に経済的にも問題は絶対ないし、日本は今までもこれからも政治的にも経済的にも世界一だし、日本は完璧だから日本にいれば人生絶対安泰だよね。」
→日本はそこまで完璧じゃないという意見が出てくる
手にいれたい彼に対して:
「彼女完璧だよね、かわいくて気が利いて、優しそうだし、体型もいいし、話し方も落ち着いてるし、笑顔がかわいくて、感情的にならないし、ちゃんとした仕事ついてて仕事もできそうだし、料理とかも絶対上手そうだし、家事も全部完璧にこなしそうだし、欠点なんて100%絶対ないし、最高だよね、世界一の彼女だね。」
→いや、欠点はあるという意見が出てくる
勉強しない子供に対して:
「勉強なんてしなくていいと思うよ。高卒でも成功している人はいるし、勉強なんてまったくしなくていいよ。勉強したところで意味ないよ。勉強なんかしなくていいよ。義務教育が終わったらすぐ働き出したらいいと思うよ。」
→それはそれで不安という感情が生まれる
行き過ぎた意見に対しては、「自分の意見のレベルに戻そう」とする力が働くというのは面白いですね。
まとめ
ということで、説得する心理学を紹介しました。
まとめると、以下のとおりです。
いずれにしろ、ポイントは、「相手の意見側の味方だと相手に認識させ、懐に潜む→相手の意見に疑問を持つような種を植え付ける」ということ。
どうしても自分の思う方向に相手の意見を転換したいときに使えるテクニックです。生活の中で実践…応用して効果を確かめてみましょう。
こちらもどうぞ。
参考:
科学に基づき解明された成功の方法や心理学をどっさり盛り込んだ一冊です。この方のサイトも面白いです。
>>> Bakadesuyo.com